登録販売者、採用の現場から
- ホーム
- 登録販売者、採用の現場から
- 鎮咳薬の作用機序とは? なぜコデイン類含有製剤は小児に禁忌なのか?
鎮咳薬の作用機序とは? なぜコデイン類含有製剤は小児に禁忌なのか?
登録販売者試験の過去問(平成30年 京都府 午前)
早速、問題を見ていきましょう。
問30 鎮咳・去痰薬とその有効成分に関する記述の正誤について、正しいものはどれか。
- 鎮咳 ・去痰薬は、反射的に出る咳を鎮めることやその原因となる痰の切れをよくすることを目的とする医薬品の総称であり、喘息症状を和らげることを目的とする医薬品は含まない。
- ジヒドロコデインリン酸塩を含む医薬品は、原則、12歳未満の小児に使用しないよう注意喚起を行う必要がある。
- コデインリン酸塩は麻薬性鎮咳成分とも呼ばれる。
- ジヒドロコデインリン酸塩は、胃腸の運動を低下させる作用も示す。
http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/documents/h30mondaigozen.pdf より一部改変して抜粋
解説
問題の答えはすぐ分かりましたか? ここからは、問題の解説をしていきましょう。
1問目
「a 鎮咳・去痰薬は、反射的に出る咳を鎮めることやその原因となる痰の切れをよくすることを目的とする医薬品の総称であり、喘息症状を和らげることを目的とする医薬品は含まない。 」
この解答は 誤 です。
ポイントは「喘息症状を和らげることを目的とする医薬品は含まない」ですね。OTC医薬品は様々な種類があり含まれている成分の商品によって様々ですので、そこまで把握していないという方もいるでしょう。
しかし、このお客様から「この成分はどうやって効くの?」「喘息症状を和らげる薬」はある?と聞かれる可能性もありますので、1つ1つ成分を確認しておくことは非常に重要です。
今度よく商品を見てほしいのですが、「テオフィリン」が含まれている商品があります。テオフィリンの作用機序は覚えているでしょうか。
細かい機序は省きますが、テオフィリンは気管支を拡張することによって呼吸を楽にします。喘息症状は気管支が狭くなってしまうことにより起こりますので、テオフィリンは喘息症状を改善してくれます。
しかし、実際の現場で「喘息」と聞いた場合には既に治療中であったり、他の医薬品を服用中、あるいは既にテオフィリンを服用していることがありますので、むやみに販売することは避けましょう。
2問目
「b ジヒドロコデインリン酸塩を含む医薬品は、原則、12歳未満の小児に使用しないよう注意喚起を行う必要がある。 」
実はこの過去問は平成30年の過去問であったことから、この問題は本来は正でした。しかし、現在は 誤 になります。
今回はコデイン類が段階的に禁忌になった経緯を説明する為にちょっと意地悪な問題を選びました。では、解説していきます。
厚生労働省による2017年7月4日 の通知で、コデイン類含有製剤の「用法及び用量に関連する注意」に記載されている文言が変更になりました。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
|
「用法及び用量に関連する注意」
2 歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること |
「用法及び用量に関連する注意」
12 歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先すること |
そして、その後2019年7月9日には「してはいけないこと」が新設され、さらに「用法及び用量に関連する注意」が変更されました。
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
|
「用法及び用量に関連する注意」
12 歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先すること |
「してはいけないこと」 1.次の人は服用しないこと 12 歳未満の小児 「用法及び用量に関連する注意」 (削除) |
副作用として呼吸抑制などの危険性があり、現在は注意喚起ではなく12歳未満の小児は使用してはいけません。
3問目
「c コデインリン酸塩は麻薬性鎮咳成分とも呼ばれる。 」
この問題は簡単だと思います。正解は 正 です。
ジヒドロコデインリン酸塩も麻薬性(中枢性)鎮咳成分です。
非麻薬性(中枢性)の鎮咳成分としてはデキストロメトルファン、ジメモルファン、クロペラスチン、チペピジン、ペントキシベリンなどがあります。
鎮咳薬についてもう少し説明すると、鎮咳薬とは、肺・気道の異物刺激による「咳反射」を抑える薬物の総称です。
異物による刺激が、脳に「咳を出して異物を出す」という指令をお願いしますが、脳の指令を出す機能を鈍らせるのは中枢性鎮咳薬です。
逆に、末梢性鎮咳薬(局所麻酔薬、去痰薬など)は異物刺激が起こらないようにするものです。
4問目
「d ジヒドロコデインリン酸塩は、胃腸の運動を低下させる作用も示す。 」
こちらも基礎的な問題ですので、すでに知っていると思います。
コデイン類は胃腸の運動を低下させる作用もあり、これが原因で便秘になる可能性もあります。
便秘になる可能性もあるという事実は、OTC販売の際の情報提供でも使えると思いますので覚えておきましょう。
関連記事
-
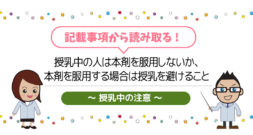
登録販売者ドタバタ劇場
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
記載される場所 この注意書きは「してはいけないこと」の項目に記載されます。このような記載がない場合には特に、不安に思ったお客様に相談をうけるケースがありますが、「してはいけないこと」や「相談すること」の項目に関連する注意 […]
-
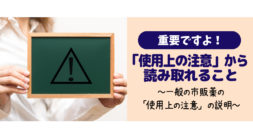
登録販売者ドタバタ劇場
「使用上の注意」から読み取れること
「使用上の注意」の重要性と記載形式 添付文書中では、「使用上の注意」は商品名など最低限の基本的情報の後に記載され、目立つよう枠で囲まれています。 また、一部は添付文書内だけでなく外箱にも記載されているため、購入前にも確認 […]
-
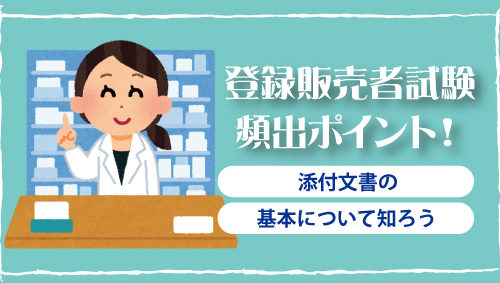
登録販売者になりたい人へ
登録販売者試験頻出!添付文書の基本について知ろう
添付文書の記載事項の構成 以下の項目からなります。実際の添付文書を見ると理解が深まります。 手元にない場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ(https://www.pmda.go.jp/Pm […]
-

登録販売者、採用の現場から
知っていますか?? 薬の添付文書の読み方
添付文書とはどのようなもの? 登録販売者として、最も医薬品の情報が凝縮されている資料とも言える添付文書。 添付文書は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称、薬機法)により、医薬品等の用法、用 […]
-
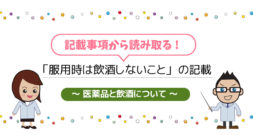
登録販売者ドタバタ劇場
服用時は飲酒しないこと
記載される項目 この注意書きは医薬品の服用時に飲酒をしないよう呼びかける禁止事項ですので「してはいけないこと」の項目に記載されています。 記載される医薬品の種類とその理由 この注意書きは特にアセトアミノフェンやアスピリン […]
-
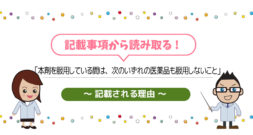
登録販売者ドタバタ劇場
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
記載される理由 この注意書きは、医薬品同士の併用による副作用を防ぐために記載されています。注意書きの文章としては、薬理学的または薬物動態学的に相互作用を起こしてしまう可能性のある医薬品を併用しないよう注意を促すものですが […]
