登録販売者、採用の現場から
- ホーム
- 登録販売者、採用の現場から
- カフェインの効果と副作用!?誰がどこまで摂取できる?
カフェインの効果と副作用!?誰がどこまで摂取できる?
カフェインとは?その効果と副作用
カフェインとは、疲労感の減少や眠気が抑制されたりと、興奮作用をもつ成分です。コーヒーやお茶などの飲料にも含まれていますが、世界中で「薬」としても広く利用されています。
薬として利用されるということは、カフェインという成分はヒトに対して著しい効果を持つ反面、副作用などのリスクもあるということだと理解できます。
副作用としては不安、震え、不眠、めまい、心拍数の増加等が知られています。また消化器管を刺激することから、下痢や吐き気、嘔吐を催すこともあります。
日本中毒学会の報告では、2011年度からの5年間の間に急性カフェイン中毒で少なくとも101人が救急搬送され、3名が死亡しています。それほどカフェインにはリスクがあることも理解しておきましょう。
カフェイン含有の飲料
農林水産省によると、下記の飲料100mlあたりに含まれるカフェイン量は:
エナジードリンク又は眠気覚まし用飲料 約32~300mg、玉露 約160mg、インスタントコーヒー 約60mg、紅茶 約30mg、煎茶/ほうじ茶/ウーロン茶 約20mgとなっているようです。
カフェインの摂取許容量
カフェインはどのくらいまで摂取していいのでしょうか。現在日本では、カフェインへの感受性は個人差が大きく正確に評価することは難しいことを考慮して、カフェインの一日摂取許容量は設定されていません。
そのため、ここでは世界各国の基準を見ながら、摂取量を考えていこうと思います。まず米国と欧州、カナダでは健康な成人であれば1日400mgまでは健康リスクは増加しないと考えられています。妊婦・授乳婦や子供に関してはこの先の項目でお話します。
妊婦・授乳婦のカフェイン摂取許容量
妊婦が高濃度のカフェインを摂取すると、胎児の発育を阻害される恐れがあるとされている為、カフェインの許容摂取量は健康な成人よりも低く設定されています。
カナダでは1日300mgは許容と評価されていますが、欧州では1日200 mgまでであれば、胎児・乳児の健康リスクは増加しないと考えられています。
子どものカフェイン摂取許容量
子どもにカフェインを摂取させたいという親御さんはあまり居ないと考えられますが、子どもの許容摂取量も考えていきましょう。
カナダでは年齢ごとに分けられており、4~6歳の子どもでは1日当たり45 mg、7~9歳では62.5 mg、10~12歳では85 mgまでと摂取量が決められています。
欧州や豪州では3 mg/kg(体重)までと、より簡略化して評価されていますのでこちらのほうが覚えやすいかもしれません。
カフェインと医薬品の飲み合わせで注意すべき点
実は、カフェインは様々の薬と相互作用することが知られています。具体的には、抗菌薬や抗血栓薬、抗うつ薬、気管支拡張薬、精神安定薬、睡眠薬等です。
そのため、もし病院で治療している病気があり、何か薬を飲んでいるようであれば、必ず医師や薬剤師に相談してもらうようにしてください。
接客例
〈バックグラウンド〉
無水カフェイン100mg含有の市販薬(1回1錠 1日3回まで)を買おうとしているお客様(21歳)からの相談
〈接客〉
お客様:すみません。試験が迫っているのでカフェインの錠剤を買って頑張ろうかと思っているのですが、これで良いですかね?あんまり飲み過ぎると危ないって聞いたことはありますが、具体的には1日どれくらい大丈夫ですか?
登録販売者:勉強を頑張っていらっしゃるのですね。勉強中の眠気や疲労感はお辛いですよね。用法用量を守って服用すれば飲み過ぎにはなりませんが、日常的になにかお茶やコーヒー等の飲み物を飲まれますか?
お客様:朝にコーヒーを飲んで、勉強中もよくコーヒーや緑茶を飲んでいます。
登録販売者:世界的には、成人は1日約400mlまでであればリスクはないと考えられています。そのため、カフェインの錠剤を1日3回飲むのであれば、コーヒーやお茶はなるべく避けるべきです。難しければ朝のコーヒーだけは許容できると考えられます。また、エナジードリンクにはカフェインが比較的多く含まれている商品が多いので、カフェインを服用中はやめておきましょう。
お客様:なるほど!ありがとうございます!
関連記事
-
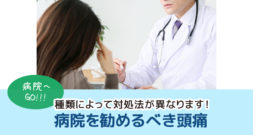
登録販売者ドタバタ劇場
こんな頭痛は要注意|病院受診を勧めるべき頭痛
頭痛は種類によって対処方法が異なる 頭痛は、一次性頭痛と二次性頭痛に分けられます。 一次性頭痛は明らかな基礎疾患のない頭痛で、代表的なものには、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛があります。片頭痛と緊張型頭痛は、症状が軽度であ […]
-

登録販売者ドタバタ劇場
登録販売者試験頻出ポイント! 登録販売者が店舗管理で気をつけたいこと
構造設備で気をつけたいこと:医薬品の陳列方法 構造設備規則によって医薬品等の陳列方法は定められ、常に正しい状態を維持するよう管理することが求められています。 商品陳列のレイアウト変更時など注意しなければいけないポイントで […]
-

登録販売者、採用の現場から
乾燥の季節到来。乾燥対策をしない場合のデメリット!
そもそも「乾燥」している状態ってどれくらいの湿度? 一般的に湿度が40%以下になってしまうと「空気が乾燥している」と判断されることが多いです。東京都の平均湿度は約50%ですが、冬はより湿度が下がります。 地域によってはさ […]
-
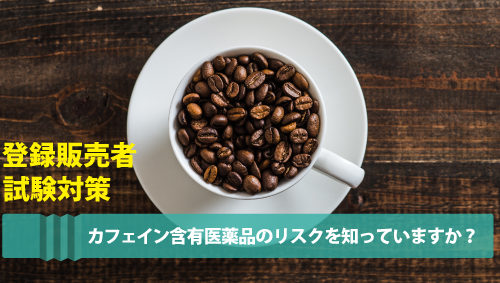
登録販売者になりたい人へ
【登録販売者試験対策】カフェイン含有医薬品のリスクを知っていますか?知っておきたいポイントを解説
カフェインとは そもそもカフェインとはアルカロイドという化合物の一種で、以下のような作用があります。 覚醒作用 血管拡張作用 交感神経刺激(基礎代謝促進)作用 胃酸分泌促進作用 利尿作用 現代でカフェイン含有として最も有 […]
-

登録販売者、採用の現場から
小児・成人・高齢者の薬物吸収・分布・代謝・排出の違いとは?
まずADMEとは? ADMEとは、体内に薬が投与されたあと、吸収されて血液中に入り、身体全体(一部)に分布し、肝臓で代謝され、尿中(糞便中)に排出される過程のことを言います。 吸収(absorption)、分布(dist […]
-

登録販売者、採用の現場から
乳幼児・高齢者は特別? 薬を服用する際に配慮が必要な理由を考えよう
乳幼児:乳児、幼児、小児の違い 医薬品の使用上の注意においては、「乳児」「幼児」「小児」という単語を意識的に使い分けされています。あくまでも目安ではありますが、年齢区分は以下のとおりです。 乳児:1歳未満 幼児:7歳未満 […]
